いま不登校の子どもに不登校から立ち直った経験談を紹介してはいけない
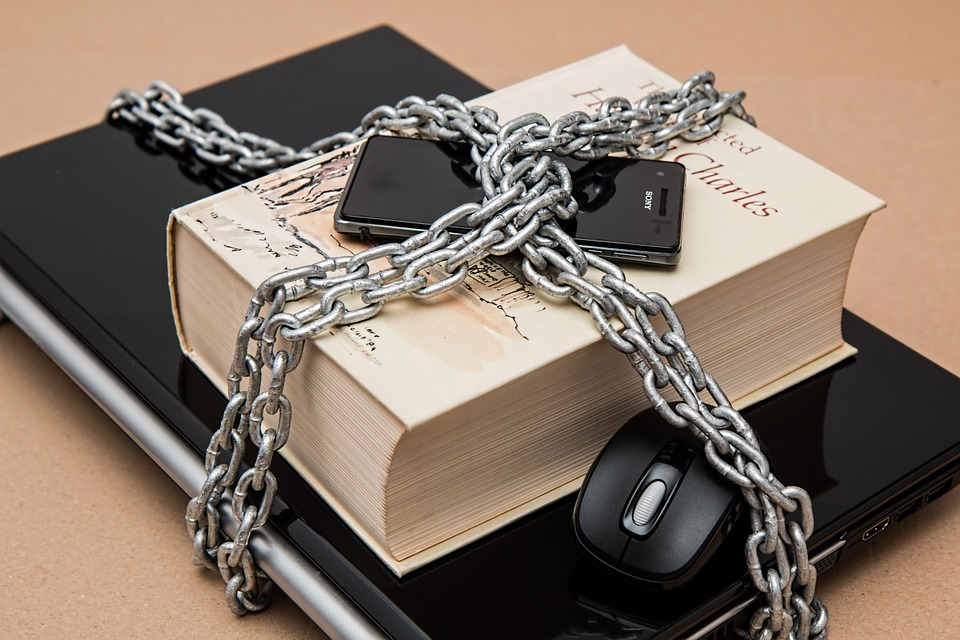
先日、学校の先生向けに不登校の講座をおこなった。
先生方への話題提供として、不登校の経験がある男性にも話してもらったのだが、2つ興味深い話があった。
1つは、不登校の理由についてランクづけしてしまうくらい不登校になったときは自信をなくしてしまうということだ。
彼は、不登校になった当時のことを気持ちをこのように話してくれた。
「いじめとか、これっていう理由じゃなくて、自分みたいにサボりに近いような理由で学校いけなくなってごめんなさいという気持ちでした。自分は勉強がきっかけだったんですけど、それくらいがんばれよって自分でも思ってました。でもがんばれないから、数ある不登校の理由の中でも自分ってしょうもないなぁって感じていました。」
不登校になったとき、いろんな理由で自信をなくしてしまうことがある。
うちの代表は部活で結果を出せないことがキッカケで自分に自信が持てなくなったと言っていた。以前インタビューさせてもらった女性は、親の期待に応えられなくて自信をなくしたと話してくれた。さらに別の方は、いじめがきっかけで友だち関係に自信が持てなくなったと言っていた。
でも、どの方も今回の男性のような、「不登校の理由でさえ大したものじゃない」という理由で自信をなくしたなんて言っていなかった。彼は高校のときに不登校になった。高校生くらいになると自分の立ち位置みたいなものを相手と比較して客観的に理解できるので、たしかにこういう理由で自信をなくすこともあるんだなぁと納得して話を聞いていた。
人が落ち込んだ時や自信をなくしたときの声かけは難しい。ポイントを外すとまったく効果を発揮しないどころか逆に反感を買ってしまうからだ。だからこそ、親や先生のみならず不登校の子どもに関わる人は、相手が自信をなくしたときに、どのポイントを押さえた声かけをしたらいいのか、それは今言うべきタイミングなのかを考えないといけない。
もし、ぼくがこの男性の先生だとしたら「大丈夫!がんばれば、すぐに成績あがるって!」と言っていただろう。そしてそれは彼から反感を買っておしまいだったはずだ。だってそういうことを言ってほしいわけじゃなかったから。
もう1つ彼が話してくれたのは、不登校しているときに誰かの不登校経験談はいらないということだ。
彼が不登校の経験談を話してくれた後に、講座に来ていただいた先生から「もし、同じような不登校の経験をしたけど立ち直った人の話があったら聞きたいと思いますか?」と質問があがった。
彼は「絶対に聞きたくないです。」と即答した。
理由はシンプルで、経験談を聞かされたらそれを満たせない自分はダメなんだと、余計に自分をダメだと思ってしまうからということだった。非常によくわかるし、まったくもってその通りだ。不登校から立ち直ったヒーローの話なんて聞きたくないのだ。
勉強でうまくいかなかった。中学受験や高校受験に失敗した。エリート校に入ったけどついていけなくなった。このような、いわゆる人生のレールから外れてしまったことで不登校になった子どもは、自分は周囲の期待に応えられなかったダメなやつだという自己イメージを持ってしまう。
このような子どもたちに必要なのは、期待に応えられない自分も自分で大丈夫だとか、そもそも周囲の期待に応えようとしていたのが間違いだったとか、周りからの期待なんて置いといて好きに生きようと思えることだ。そのために、これまでの周りからの期待に応えようとした自分を括弧にくくって自分を見つめ直す時間こそが必要だ。
だから私たちは、不登校から立ち直った経験談という形で子どもに新しいレールや期待を押し付けてはいけない。このような経験談を伝えたくなるのは往々にして親切心からだということもよく分かるけれど、そこはグッと我慢して、子どもがこれまでを見つめ直せるよう自分自身も見つめ直すようにしたい。
もちろん、大人の自分が不安だからという理由で不登校の経験談を自分が勉強するのは大切なことだ。自分が辛くなって、何も手につかなくなってしまっては元も子もないので、自分の不安を解消するためならいろんな人の経験談を読んでみてほしい。
不登校から立ち直ったヒーロー話は不要だが、同じ不登校の子どもがいる場所を紹介することは子どもにとって有効らしい。それは先に述べた不登校経験者へのインタビューで教えてもらった。
年代や性別を問わず、同じ立場の子どもがいる場所に通うようになるといろんなことが落ち着いてきて、人によっては教室に戻るし、進学に向けて勉強し始めたりしたそうだ。場所もなんでもよさそうだ。学校にある別室登校や保健室登校、市町の適応指導教室、あるいはフリースクールでも良い。
別室登校や保健室登校だと、同じ学校の生徒からどう思われるか気になって最初は行きづらいらしいけれど、すでに利用している生徒と何かしらの共通点があればそのハードルは下がる。いじめがキッカケで不登校になったと答えてくれた方も、別室登校にはじめは抵抗があったが同じ部活の生徒がいると知ってから別室登校をするようになったそうだ。
不登校に限らず、子育てや教育に誰にでも通じる正解なんてない。「子どもを東大に入れたママの教育法」とか、「水嫌いを克服する方法」とか、「有名塾講師の熱血指導」なんてものは全員に通じないでしょう。成功法なんてものは基本的にローカルな一部分でしか通じない。
だから目の前の子どもに何が合うかはアレコレ試してみるしかない。気が遠くなりそうだが、今回はこれをしたら失敗するというヒントを得た。不登校から立ち直った経験談は、いま不登校の子どもには聞かせてもしょうがないということだ。
不登校のおはなし会のお知らせ
8/26(日)教育支援センターの先生と考える不登校の子どもの育ちと学び
– 不登校のおはなし会 in 滋賀 vol.13 –
■ こんなかたにオススメ
・教育支援センター(適応指導教室)がどんな場所か知りたい。
・子どものことについて同じ立場で話せる人が欲しい。
・もし自分がセンターを利用できるならどうすればいいか知りたい。
・子どもの今後のことについて見通しが持てるきっかけが欲しい。
・二学期からどうすればいいか悩んでいる。
■ イベント概要
◎日時 8月26日(日) 14:00~16:30
◎参加費 1000円
◎プログラム
・自己紹介
・フリースクール昼TRY部スタッフの話題提供
・テーマについてゲストから話題提供
・参加者みんなでお話す時間
・ふり返りやアンケートなど
◆ 話題提供
草津市教育研究所 指導主事
嶋田達也(しまだたつや)先生
◎対象 不登校のお子さんがいる保護者さん
◎定員 10名(先着順)
◎会場 場所: コワーキングスペース Mag House (JR瀬田駅3分)
滋賀県大津市大萱一丁目9−7ワイエムビル202
◎お申し込み
・メールでのお申し込み 件名を「8/26不登校のおはなし会参加」とし、 本文に、お名前・ご住所・ご連絡先を明記のうえ、info@dlive.jp にメールをお送りください。
※ こちらからのお返事が届かないケースが増えております。迷惑メール対策をされている方は特に、info@dlive.jp のメールが届くよう設定をお願いいたします。
主催 NPO法人D.Live
お問い合わせ先 info@dlive.jp
































